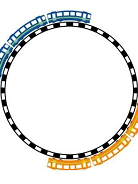電車は開いた扇のふちを走る
1
電車は開いた扇のふちを走る。
電車の中では横から景色を見る。それは単に座席が横にあり、そこに客が正面を向いて座っているというだけのことである。しかし、見るものにとって、窓に映る景色は、右から左へと流れている。
斜めの田畑、ビニールハウス、家々、工場、がらくた置き場、六分咲きの桜、ハクモクレン、椿の生け垣。瞬く間に過ぎて行く。広い桑畑が割と長く視界にとどまることもある。それもほんの数秒にすぎない。景色はひたすらに流れて行く。見ていると、そのうちに視界にとどまるものの時間的な差があることに気づいた。一番短い時間で視界から消えるのは電信柱である。それは、窓に非常に近いところで、時々ちらっちらっと一定の間隔で横切る。電信柱の完全な形は目にも止まらない。尾を引いて矢のように過ぎ行くその残像だけが目に映る。僕は猫じゃらしでかまわれた猫のように、目をきょろきょろさせてそれを見ている。遠くの観覧車が視界に入ってきた。観覧車はゆっくりゆっくりまいまいのように移動している。飛ぶようなめまぐるしさで去っていく電信柱。浮かび上がる朝日のように位置を変えていく観覧車。
僕はそのうちに妙な気分に襲われた。僕の視界は一枚のキャンバスであり、いかに遠いものを小さく描いて、また近いものを大きく描いたとしても、定規を当ててみれば平面上のどの二点間も公平に同じ距離でなければならない。だから、仮に視界のキャンバスを横にさっと移動させてみたところで、近くのものが遠くのものより先に視界から消えるということは考えられない。ところが、今僕の目の前の景色は僕の内部にある原則に従っていないではないか。近くの家並みは急いで過ぎ去る。遠くの酪農家のサイロはゆったりゆったり流れて行く。遙かなる山脈は微動だにしない。この速度の違いは一体なんだろう?
そう思ったら僕は怖くなってきた。いや、僕はこんなことを知らなかったのではない。今までは無意識に肯定していたし、今だって当たり前じゃないかと受け止めることはできる。僕が怖いのはそんなことではなくて、人はふとしたきっかけで思考の迷路に落ち込めるということだ。一度そこに踏み込むと、まるっきり手に負えなくなる。それは人間が自分の死の不合理さに気づき苦悩するのと似ている。あえて意識しなければ健康でいられるのに、いったん意識の上に昇らせるとあとには戻れない。底なし沼に吸い込まれるだけである。
駅のホームにかかった歩道橋を渡り、生け垣に挟まれた小道をつきあたると小さなアパートが正面を向いている。僕と妻の部屋は一〇三号室、二階建ての下の五部屋の真ん中だ。僕が出勤するとドアの前で僕の妻が手を振る。顔が小さくて姿勢が良いので、僕は妻を見るといつもリスを思い浮かべる。妻は、明るい色の薄い布地のシャツに清潔な感じのするエプロンをかぶっている。十日前には考えられない薄着だ。近所の梅の花はほとんど散ってしまった。三月も終わるのだ。僕の会社は年度末の整理に追われ忙しい。
電車の中では横から景色を見る。それは単に座席が横にあり、そこに客が正面を向いて座っているというだけのことである。しかし、見るものにとって、窓に映る景色は、右から左へと流れている。
斜めの田畑、ビニールハウス、家々、工場、がらくた置き場、六分咲きの桜、ハクモクレン、椿の生け垣。瞬く間に過ぎて行く。広い桑畑が割と長く視界にとどまることもある。それもほんの数秒にすぎない。景色はひたすらに流れて行く。見ていると、そのうちに視界にとどまるものの時間的な差があることに気づいた。一番短い時間で視界から消えるのは電信柱である。それは、窓に非常に近いところで、時々ちらっちらっと一定の間隔で横切る。電信柱の完全な形は目にも止まらない。尾を引いて矢のように過ぎ行くその残像だけが目に映る。僕は猫じゃらしでかまわれた猫のように、目をきょろきょろさせてそれを見ている。遠くの観覧車が視界に入ってきた。観覧車はゆっくりゆっくりまいまいのように移動している。飛ぶようなめまぐるしさで去っていく電信柱。浮かび上がる朝日のように位置を変えていく観覧車。
僕はそのうちに妙な気分に襲われた。僕の視界は一枚のキャンバスであり、いかに遠いものを小さく描いて、また近いものを大きく描いたとしても、定規を当ててみれば平面上のどの二点間も公平に同じ距離でなければならない。だから、仮に視界のキャンバスを横にさっと移動させてみたところで、近くのものが遠くのものより先に視界から消えるということは考えられない。ところが、今僕の目の前の景色は僕の内部にある原則に従っていないではないか。近くの家並みは急いで過ぎ去る。遠くの酪農家のサイロはゆったりゆったり流れて行く。遙かなる山脈は微動だにしない。この速度の違いは一体なんだろう?
そう思ったら僕は怖くなってきた。いや、僕はこんなことを知らなかったのではない。今までは無意識に肯定していたし、今だって当たり前じゃないかと受け止めることはできる。僕が怖いのはそんなことではなくて、人はふとしたきっかけで思考の迷路に落ち込めるということだ。一度そこに踏み込むと、まるっきり手に負えなくなる。それは人間が自分の死の不合理さに気づき苦悩するのと似ている。あえて意識しなければ健康でいられるのに、いったん意識の上に昇らせるとあとには戻れない。底なし沼に吸い込まれるだけである。
駅のホームにかかった歩道橋を渡り、生け垣に挟まれた小道をつきあたると小さなアパートが正面を向いている。僕と妻の部屋は一〇三号室、二階建ての下の五部屋の真ん中だ。僕が出勤するとドアの前で僕の妻が手を振る。顔が小さくて姿勢が良いので、僕は妻を見るといつもリスを思い浮かべる。妻は、明るい色の薄い布地のシャツに清潔な感じのするエプロンをかぶっている。十日前には考えられない薄着だ。近所の梅の花はほとんど散ってしまった。三月も終わるのだ。僕の会社は年度末の整理に追われ忙しい。