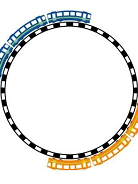電車は開いた扇のふちを走る
4
ところが、だんだんこの世界に違和感を覚えるようになってきた。妻と会話しても同僚や上司と会話しても以前のように共感できないのだ。表面的にはとてもきちんとしたことを言うのだけれど、気持ちとか中身が伝わってこなくて機械と話をしているようなのだ。
「ご注文の時は1、ご注文しないときは9を押して、最後に#を押してください」
そんな感じなのだ。必要のあるやりとりしかしない。誰もが一つのことだけを目的にして余分な会話や行為というものは存在しない。矛盾とか対立とかは一切ない。だってみんな同じ意見なのだから。新聞を読んでみたらいくつかの政党の主張があったが、どの政党もつまるところはおなじであった。驚いたことに、本屋で代表的な作家の名作を少し読んでみたら、僕が元の世界で読んだものとはところどころ表現に違いがあって、主題が違ったものになっていた。しかも、この世界では、夏目漱石の『吾輩は猫である』も志賀直哉の『城の崎にて』も太宰治の『ヴィヨンの妻』も三島由紀夫の『潮騒』もすべて同じ主題だった。ジャンルは分けられ、作家も作品名も違うが、中身は一緒なのである。誰と話をしても同じ考えしか引き出せなかった。誰も自分というものを持っていない。自分にしかできないことを自分のやり方でする人はどこにもいない。全体が一つであり、個人は全体をつくるための一つの部分であった。僕は、この世界をそのようにさせるヒットラーとかスターリンのような存在があるのではないかと探してみたが見当たらなかった。誰もがごく自然に一つのものの見方しかしないのだ。そして何の疑いも持っていない。
僕はこの世界にいることに耐えられなくなってきた。みんなの考えに従っていれば楽である。もめごとは決して起こらないし、仲違いして口を利かなくなることはありえない。平和で幸福で明るく豊かな人生である。しかし、そのどれもが自分の考えではないのだ。自分で見つけたものではない。自分で生み出したものではない。自分にしかないものを少しでも彼らの前に出してみよう。この世界の平和はその瞬間から消え失せるだろう。
会社で、僕の仕事は僕のやり方では通用しなくなった。僕は、この世界で生きていた僕がこの世界の目的にかなったやり方でやってきた仕事を引き継ぐしかなかった。同僚や上司や得意先との関係も一つの世界観の内部原則に従うほかなかった。
家に帰っても同じだった。この世界に生きていた僕の持ち物は全く僕の興味を引かなかった。他の誰かの持ち物と変えても何の差し障りもないと思われた。大体妻からしてさえそうであった。この妻でなくてはならないという気が全く起こらない妻であった。自分のいた世界の妻と何もかも同じなのに、愛することができないのだ。こんな妻なら誰でも同じだと思ってしまう。しかしこの妻は何も知らないから、僕に対してとてもよく尽くしてくれる。僕はこの世界で独りぼっちで寂しいから、優しいその妻に甘えてしまった。愛することができないのに、毎夜のごとく妻を求めてしまった。
「ご注文の時は1、ご注文しないときは9を押して、最後に#を押してください」
そんな感じなのだ。必要のあるやりとりしかしない。誰もが一つのことだけを目的にして余分な会話や行為というものは存在しない。矛盾とか対立とかは一切ない。だってみんな同じ意見なのだから。新聞を読んでみたらいくつかの政党の主張があったが、どの政党もつまるところはおなじであった。驚いたことに、本屋で代表的な作家の名作を少し読んでみたら、僕が元の世界で読んだものとはところどころ表現に違いがあって、主題が違ったものになっていた。しかも、この世界では、夏目漱石の『吾輩は猫である』も志賀直哉の『城の崎にて』も太宰治の『ヴィヨンの妻』も三島由紀夫の『潮騒』もすべて同じ主題だった。ジャンルは分けられ、作家も作品名も違うが、中身は一緒なのである。誰と話をしても同じ考えしか引き出せなかった。誰も自分というものを持っていない。自分にしかできないことを自分のやり方でする人はどこにもいない。全体が一つであり、個人は全体をつくるための一つの部分であった。僕は、この世界をそのようにさせるヒットラーとかスターリンのような存在があるのではないかと探してみたが見当たらなかった。誰もがごく自然に一つのものの見方しかしないのだ。そして何の疑いも持っていない。
僕はこの世界にいることに耐えられなくなってきた。みんなの考えに従っていれば楽である。もめごとは決して起こらないし、仲違いして口を利かなくなることはありえない。平和で幸福で明るく豊かな人生である。しかし、そのどれもが自分の考えではないのだ。自分で見つけたものではない。自分で生み出したものではない。自分にしかないものを少しでも彼らの前に出してみよう。この世界の平和はその瞬間から消え失せるだろう。
会社で、僕の仕事は僕のやり方では通用しなくなった。僕は、この世界で生きていた僕がこの世界の目的にかなったやり方でやってきた仕事を引き継ぐしかなかった。同僚や上司や得意先との関係も一つの世界観の内部原則に従うほかなかった。
家に帰っても同じだった。この世界に生きていた僕の持ち物は全く僕の興味を引かなかった。他の誰かの持ち物と変えても何の差し障りもないと思われた。大体妻からしてさえそうであった。この妻でなくてはならないという気が全く起こらない妻であった。自分のいた世界の妻と何もかも同じなのに、愛することができないのだ。こんな妻なら誰でも同じだと思ってしまう。しかしこの妻は何も知らないから、僕に対してとてもよく尽くしてくれる。僕はこの世界で独りぼっちで寂しいから、優しいその妻に甘えてしまった。愛することができないのに、毎夜のごとく妻を求めてしまった。