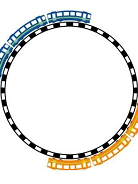電車は開いた扇のふちを走る
7
自分の世界に戻るのは今だと思った。
朝、僕はいつものように僕たちの部屋103号室を出た。安らぎの部屋だった。親密さで満ち足りた空間だった。それが、たとえ本当の自分の妻ではないと言え、この世界の妻とうまくいかなくなり、うそ寒く、ぎこちない雰囲気の部屋になってしまった。その部屋を出る。いいさ、元の世界に戻れば何もかも元通りになるんだ。
もう六月だった。田植えが始まっている。深緑が手足を伸ばしている。花の少ない季節だ。ところで全然関係のない話題だが、自然界には無駄がない。ボルネオ島のイチジクは不思議だ。実の中に咲く花に雌ばちが入り込み、花の中に卵を産み付け死ぬ。育った雄ばちは羽がなく雌ばちと交尾し終えると実の表面までトンネルを掘り死ぬ。雌はそのトンネルを抜けて別のイチジクまで飛ぶ。このイチジクは一年中実をつける。他の植物の実がない時に多くの森の動物の命を支えているのだ。雄は羽がなく一生イチジクから出られないが、食物連鎖の中で重要な役割を果たしている。こんな特殊な例を挙げなくても、自然界のサイクルに無駄がないのは周知の事実だ。唯一無駄を生み出すのは人間だ。人間性、文化、余暇、こういったものは自然界の原則を第一主義にした世界では不要で廃されるべきものなのだ。
ホームに立ち、電車に入り、外を眺めた。よく晴れていて緑がまぶしい。自然の世界は悪くない。だけど、ぼくにはまだそういった心境に完全には共感できない。変な言い方だが、ことさら僕は小さい頃から夏炉冬扇を求めて生きてきたんだから。余分なことをあれこれと大真面目に想像して一人で笑い転げるのが好きなんだ。そういうものの中には他の誰かにも共感を持ってもらえることが多少ある。ひょんなことからすばらしい世界が生まれることもある。それを大勢の人々と共感できたらどんなにいいだろう。ビートルズの生み出した世界。フィッツジェラルドの生み出した世界。その他にもたくさんあるし、人それぞれに違うけれど、そういう世界を誰もがしみじみと味わうことができる世界に僕は住みたい。僕は戻る。両側のつり革につかまって、まっすぐに立った。一方の景色を視野にとらえた。もう一方の景色を少しずつ視野に入れてみた。予想した通り頭がグラグラしない。両方の景色が完全につり合った。その状態の保持に全集中力を使った。この世界に入り込むときの確かな感触と同じ感触がついにやって来た。と同時に、この世界に来る時と同様に、電車が脱線した。僕は急いで外に出た。
元に戻った。妻も会社の同僚も上司も元のままだった。何もかもが元通りになった。
妻は僕の冗談に応じたり、笑ったりしてくれる。会社では僕なんかよりずっと上手な冗談やきつい冗談が飛び交っている。みんな持論を展開してやりあっている。僕のやり方で仕事ができる。僕はノロマだけどノルマは達成するし、自分で言うのはおかしいが、僕の仕事に満足して信頼を寄せてくれる人が多い。自分のやり方が信頼を得られるということはとてもうれしい。自信につながる。
朝、僕はいつものように僕たちの部屋103号室を出た。安らぎの部屋だった。親密さで満ち足りた空間だった。それが、たとえ本当の自分の妻ではないと言え、この世界の妻とうまくいかなくなり、うそ寒く、ぎこちない雰囲気の部屋になってしまった。その部屋を出る。いいさ、元の世界に戻れば何もかも元通りになるんだ。
もう六月だった。田植えが始まっている。深緑が手足を伸ばしている。花の少ない季節だ。ところで全然関係のない話題だが、自然界には無駄がない。ボルネオ島のイチジクは不思議だ。実の中に咲く花に雌ばちが入り込み、花の中に卵を産み付け死ぬ。育った雄ばちは羽がなく雌ばちと交尾し終えると実の表面までトンネルを掘り死ぬ。雌はそのトンネルを抜けて別のイチジクまで飛ぶ。このイチジクは一年中実をつける。他の植物の実がない時に多くの森の動物の命を支えているのだ。雄は羽がなく一生イチジクから出られないが、食物連鎖の中で重要な役割を果たしている。こんな特殊な例を挙げなくても、自然界のサイクルに無駄がないのは周知の事実だ。唯一無駄を生み出すのは人間だ。人間性、文化、余暇、こういったものは自然界の原則を第一主義にした世界では不要で廃されるべきものなのだ。
ホームに立ち、電車に入り、外を眺めた。よく晴れていて緑がまぶしい。自然の世界は悪くない。だけど、ぼくにはまだそういった心境に完全には共感できない。変な言い方だが、ことさら僕は小さい頃から夏炉冬扇を求めて生きてきたんだから。余分なことをあれこれと大真面目に想像して一人で笑い転げるのが好きなんだ。そういうものの中には他の誰かにも共感を持ってもらえることが多少ある。ひょんなことからすばらしい世界が生まれることもある。それを大勢の人々と共感できたらどんなにいいだろう。ビートルズの生み出した世界。フィッツジェラルドの生み出した世界。その他にもたくさんあるし、人それぞれに違うけれど、そういう世界を誰もがしみじみと味わうことができる世界に僕は住みたい。僕は戻る。両側のつり革につかまって、まっすぐに立った。一方の景色を視野にとらえた。もう一方の景色を少しずつ視野に入れてみた。予想した通り頭がグラグラしない。両方の景色が完全につり合った。その状態の保持に全集中力を使った。この世界に入り込むときの確かな感触と同じ感触がついにやって来た。と同時に、この世界に来る時と同様に、電車が脱線した。僕は急いで外に出た。
元に戻った。妻も会社の同僚も上司も元のままだった。何もかもが元通りになった。
妻は僕の冗談に応じたり、笑ったりしてくれる。会社では僕なんかよりずっと上手な冗談やきつい冗談が飛び交っている。みんな持論を展開してやりあっている。僕のやり方で仕事ができる。僕はノロマだけどノルマは達成するし、自分で言うのはおかしいが、僕の仕事に満足して信頼を寄せてくれる人が多い。自分のやり方が信頼を得られるということはとてもうれしい。自信につながる。